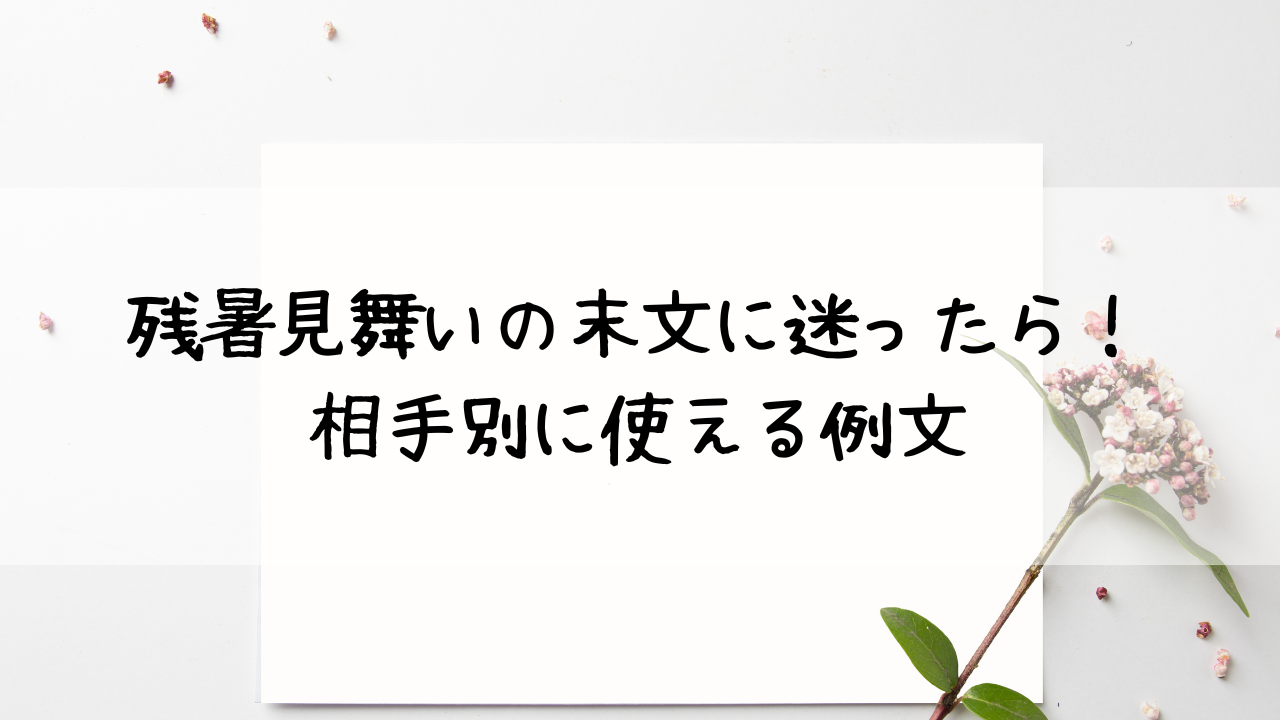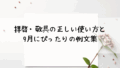残暑見舞いを書くときに意外と迷ってしまうのが「末文(結びの言葉)」。相手の心に残る一通にするには、最後の一言がとても大切です。
この記事では、「残暑見舞いの末文」に特化し、友人・ビジネス相手・目上の方などシーン別にすぐ使える例文を多数ご紹介。
さらに、書き方の基本構成やNG表現、相手に響く自然な文章のコツまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
2025年の立秋(8月7日)を過ぎたら、この記事を参考に残暑見舞いを準備しましょう。マナーを押さえつつ、あなたの“気遣い”をしっかり伝えるための完全ガイドです。
残暑見舞いの末文とは?意味と役割
残暑見舞いの「末文(まつぶん)」とは、手紙の最後に添える結びの言葉のことです。単なる形式的なものに見えて、実は相手への思いやりや礼儀が最も表れるパートでもあります。この章では、末文が持つ役割や意味について分かりやすくご紹介します。
なぜ末文が大切なのか
残暑見舞いは、暑さの残る季節に相手を気遣う手紙です。その中でも末文は「心の余韻」を残す最終パート。たとえば「お身体ご自愛くださいね」と書かれていたら、それだけで少しホッとしますよね。
このように末文には、文章全体の印象を左右する力があります。逆に、締めくくりが雑だと、せっかく丁寧に書いた文章も台無しになってしまうことも。
残暑見舞いの末文は、気遣いと余韻を伝える“最後のひと押し”なのです。
残暑見舞い全体の構成と末文の位置づけ
まずは、残暑見舞いの一般的な構成を押さえておきましょう。以下の4つのパートに分かれます。
| パート | 内容 |
|---|---|
| ① 季節のあいさつ | 「残暑お見舞い申し上げます」など、書き出しの一言 |
| ② 本文 | 近況報告や感謝、相手の健康を気遣う言葉 |
| ③ 末文 | 今後の健康を祈る言葉や丁寧な締めくくり |
| ④ 日付 | 「令和○年 晩夏」など、季節を示す表現 |
つまり、末文は手紙全体のまとめ役。そのため、内容が抽象的すぎたり、相手にそぐわない言葉遣いだと違和感を持たれてしまいます。
文章全体のトーンや、相手との関係性に合わせた表現を選ぶことがとても大切なのです。
次の章では、残暑見舞いの時期やマナーについても詳しく見ていきましょう。
残暑見舞いを送る時期とマナー
残暑見舞いは、送るタイミングや言葉選びに少し注意が必要な季節のあいさつ状です。この章では、いつ送るのが正解なのか、どんなマナーに気をつければいいのかを詳しく解説していきます。
送る時期の目安(立秋から8月末まで)
残暑見舞いを送る時期は「立秋(8月7日ごろ)」から「8月末まで」が基本です。
立秋とは、暦の上で「秋の始まり」とされる日ですが、実際にはまだまだ暑さが続く時期。この時期に届くように手紙を出すのが、残暑見舞いの正しいタイミングとされています。
| 見舞いの種類 | 送る時期 | 適切な表現 |
|---|---|---|
| 暑中見舞い | 梅雨明け〜立秋前(7月中旬〜8月6日頃) | 「暑中お見舞い申し上げます」 |
| 残暑見舞い | 立秋〜8月末 | 「残暑お見舞い申し上げます」 |
9月に入ってしまうと季節外れと感じられる場合もあるので、なるべく8月中旬までには準備を始めておきましょう。
相手別に考える敬語・言葉選び
残暑見舞いは、送る相手によって言葉の使い方にも違いが出てきます。親しい友人に対してはカジュアルに、ビジネス相手や目上の方には丁寧な表現が求められます。
| 相手 | 使いたい敬語・表現の例 | 避けたい言い回し |
|---|---|---|
| ビジネス相手 | 「ご自愛のほどお願い申し上げます」 「貴社のご発展を祈念いたします」 |
「元気でね」「また会いましょう」などのカジュアル表現 |
| 目上の方・恩師 | 「お健やかにお過ごしのことと存じます」 「ご自愛くださいませ」 |
「暑いですね〜」「お元気ですか?」など馴れ馴れしい言葉 |
| 友人・知人 | 「まだまだ暑いけど、元気で過ごしてね」 「また涼しくなったら会おう」 |
堅すぎるビジネス調や文語体 |
相手の立場や関係性に応じて、自然な言葉を選ぶことが、マナー以上に心遣いとして伝わります。
次の章では、残暑見舞いの中でも重要な「末文(結び)」をどう書けばよいのか、具体的なポイントを解説していきます。
残暑見舞いの末文作成ポイント
残暑見舞いの文章で、最後に書く「末文(結びの言葉)」は、相手の心に残る部分です。この章では、相手に寄り添った言葉を選ぶためのポイントを、分かりやすくご紹介します。
相手の健康を気遣う表現
残暑見舞いの末文で一番大切なのは、相手の体調を思いやる一言です。たとえば、以下のような表現があります。
| 表現例 | 使う場面 |
|---|---|
| 「くれぐれもご自愛ください」 | すべての相手に使える万能表現 |
| 「健康には十分ご留意くださいませ」 | ビジネス・目上の方に丁寧な印象を与えたいとき |
| 「体調を崩されませんように」 | 親しい相手や友人向け |
「ご自愛ください」は、自分を大切にしてくださいという意味の敬語表現で、季節のあいさつ状では非常に頻繁に使われます。
季節感を盛り込む言い回し
残暑見舞いは「夏の終わりから秋のはじまり」のタイミングに送るもの。だからこそ、季節の移ろいを感じさせるフレーズを入れると、文章がグッと洗練されます。
- 「秋風が感じられる頃となりましたが…」
- 「朝夕は幾分かしのぎやすくなってまいりましたが…」
- 「蝉の声に代わり、虫の音が聞こえてまいりました…」
こういった自然や気候を絡めた表現を使うと、文章全体に季節感が出て、相手にも心地よく届きます。
ビジネス・友人・目上など場面別の配慮
相手によって、選ぶ言葉のトーンは大きく変わります。ここでは、ケース別に適した末文の書き方を比較してみましょう。
| 場面 | 適した末文の例 | ポイント |
|---|---|---|
| ビジネス | 「時節柄、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます」 | フォーマルさと敬意を忘れずに |
| 目上・恩師 | 「暑さ厳しき折、ご自愛専一にてお過ごしくださいませ」 | 丁寧語や美しい日本語を用いる |
| 友人・親しい人 | 「また落ち着いたら会いましょう。元気でね」 | 距離の近さを大切に、自然体な表現を |
どんな言葉が相手に一番響くかを想像しながら末文を考えると、自然と心のこもった文章になりますよ。
次の章では、実際に使える末文の「例文」を相手別にたっぷりご紹介します。
残暑見舞いの末文 例文集【相手別】
この章では、実際に使える「末文(結びの言葉)」を、相手の立場別に分類してご紹介します。相手に合わせた一言を選ぶだけで、残暑見舞いの印象がぐっと良くなりますよ。
一般向けの末文例
幅広い相手に使える定番の表現です。迷ったときはこちらから選ぶと安心です。
| 例文 | 特徴 |
|---|---|
| まだまだ暑さが続きますので、どうかご自愛くださいませ。 | 柔らかく丁寧。誰にでも使いやすい |
| 厳しい残暑が続きますが、くれぐれもお身体にお気をつけください。 | ややフォーマルな印象。ビジネスにも対応可 |
| 残暑厳しき折、健康には十分ご留意のほどお願い申し上げます。 | やや格式高い。目上の方やビジネス向け |
ビジネス相手向け末文例
社外の取引先や上司など、ビジネスシーンでは敬意とフォーマルさが重視されます。
- 時節柄、ご健康に留意されますようお願い申し上げます。
- 今後とも変わらぬご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。
- 末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
これらの表現は格式がありつつも定番なので、あらゆるビジネス相手に安心して使えます。
目上の方・恩師向け末文例
先生や先輩など、お世話になった方への手紙では、敬語と控えめな表現が基本です。
- 暑さ厳しき折、くれぐれもお身体大切にお過ごしくださいませ。
- 秋風の訪れを感じる頃、お元気でお過ごしのことと存じます。
- 今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
特に恩師には、「ご自愛ください」だけでなく「ご指導への感謝」や「再会への願い」を込めると印象が深まります。
友人・知人向け末文例
親しい相手には、少しくだけた自然な言葉遣いで構いません。無理にフォーマルにしすぎないことがポイントです。
- まだまだ厳しい暑さが続きますが、元気でお過ごしくださいね。
- 涼しくなるころになりましたら、またお会いできると嬉しいです。
- 季節の変わり目ですので、体調を崩されませんように。
感情が伝わる自然体の文章が、距離感を縮めてくれますよ。
次の章では、こうした末文を活用した「残暑見舞いの全文例」をご紹介します。文章全体の流れが分かると、より書きやすくなりますよ。
末文に繋げる残暑見舞いの全文例
ここでは、先ほど紹介した末文の表現を実際の残暑見舞いにどう使うか、文章全体の流れが分かる「全文例」としてご紹介します。相手別に3パターン用意しましたので、シーンに合わせて参考にしてください。
友人向け全文例
| 残暑お見舞い申し上げます。
立秋を過ぎてもまだまだ暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。 まだまだ厳しい暑さが続きますが、元気でお過ごしくださいね。 |
ビジネス向け全文例
| 残暑お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 時節柄、ご健康に留意されますようお願い申し上げます。 |
目上の方向け全文例
| 残暑お伺い申し上げます。
暦の上では秋となりましたが、まだまだ暑さが続いております。 暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛専一にてお過ごしくださいませ。 |
このように末文は、文章全体の「締め」として自然に繋がる形で使うのが理想的です。
次の章では、文章作成の際に気をつけたい注意点や避けるべき表現について解説します。
書き方の注意点とNG表現
残暑見舞いは丁寧に書いていても、ちょっとした言葉遣いのズレで、相手に違和感を与えてしまうことがあります。この章では、よくあるNG表現や、避けたいポイントをケース別にご紹介します。
季節感を損なう言葉
残暑見舞いは「秋のはじまり」だけど「まだ暑い」という微妙な時期に送ります。そのため、暑中見舞いや秋便りと混同した言葉を使わないよう注意が必要です。
| 避けたい表現 | 理由 |
|---|---|
| 「暑中お見舞い申し上げます」 | 立秋以降は「残暑見舞い」が正しい |
| 「秋風が心地よい季節ですね」 | 秋の深まりを思わせる表現は早すぎる |
| 「もうすぐ年の瀬ですね」 | 季節感が飛びすぎており不自然 |
残暑見舞いのタイミングは8月中旬~下旬。「夏の終わりらしい、でもまだ暑い」という表現を意識しましょう。
カジュアル過ぎる・固すぎる文章のバランス
相手との関係性に合っていない言葉遣いは、やはり違和感の原因になります。とくに、ビジネスシーンでフランクすぎたり、逆に親しい相手に敬語が過剰だったりすると、気持ちが伝わりにくくなります。
| ケース | NG表現 | 改善例 |
|---|---|---|
| ビジネス相手に | 「暑いですね~。体調には気をつけてくださいね!」 | 「時節柄、ご自愛のほどお願い申し上げます。」 |
| 親しい友人に | 「ご健勝をお祈り申し上げます。」 | 「また涼しくなったら会おうね。」 |
相手に合った「距離感のある言葉」を選ぶことが、自然で心のこもった残暑見舞いには欠かせません。
次はいよいよ最終章。残暑見舞いをより印象深く、心温まるものに仕上げるコツをお伝えします。
まとめと残暑見舞いをもっと心温まるものにするコツ
ここまで残暑見舞いの書き方や末文の例文、注意点などを解説してきましたが、最後にもう一歩踏み込んで「相手の心に残る」残暑見舞いを仕上げるためのコツをまとめておきましょう。
| ポイント | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 手書きのひと言を添える | 印刷でも、最後に数行だけでも直筆で書くと、グッと温かみが増します |
| 思い出や共通の話題を盛り込む | 「この前の〇〇、楽しかったですね」などの具体的なエピソードを入れると◎ |
| 相手の近況に寄り添う | 「お仕事お忙しいと聞きましたが、お身体ご無理なさいませんように」など |
| 季節のモチーフを取り入れる | セミ、夕立、ひまわり、風鈴など、夏の風物詩を文章に加える |
こうした小さな気配りが、残暑見舞いを“ただの形式”から“心の贈り物”に変えてくれます。
そして何よりも大切なのは、相手を思う気持ちを込めることです。きれいな言葉より、伝えたい気持ちがにじむ文章の方が、読む人の心には残ります。
残暑見舞いは、日本らしい「思いやりの文化」の一つ。この記事を参考に、あなただけのあたたかい一通を完成させてくださいね。