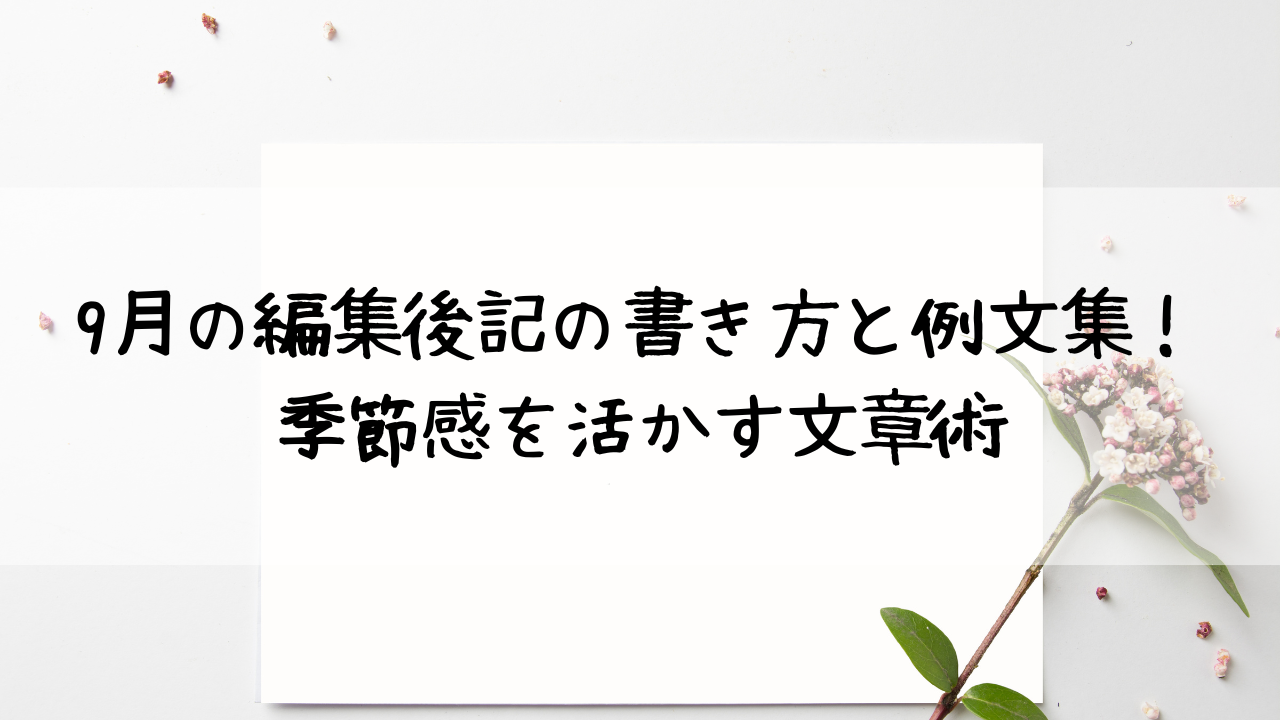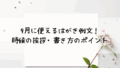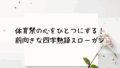9月は、夏の暑さがようやく和らぎ、秋の気配が感じられる季節。広報誌や社内報、メルマガなどの編集後記でも、この季節感を文章に反映させることで、読者との心の距離をぐっと近づけることができます。
この記事では、「編集後記とは何か?」という基本から、9月に適した時候の挨拶、風物詩、実用的な例文、そして書き方のコツまでを丁寧に解説。読みやすく、共感を呼ぶ編集後記を目指すあなたに役立つ情報を網羅しています。
秋の始まりを感じさせる一文で、読者の心に余韻を残す編集後記を一緒に作りましょう。
9月の編集後記とは?役割と魅力
この章では、「編集後記とはそもそも何か?」という基本から、9月ならではの魅力までを分かりやすく解説します。季節に寄り添った編集後記の価値を再発見していきましょう。
編集後記の基本的な目的と役割
編集後記は、広報誌や社内報、メルマガなどの最後に掲載される“締めくくりのひとこと”です。形式ばらない個人的なコメントで、読者との距離をぐっと縮める役割を担います。
たとえば、「今号もお読みいただきありがとうございました」といった挨拶や、「特集記事を制作するうえで印象的だったこと」など、発信者の“声”を届けることで、誌面全体に温かみを添えるのが特徴です。
| 編集後記の主な役割 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 読者との接点をつくる | 発信者の人柄を伝えることで、親近感を生む |
| 誌面全体の印象をまとめる | トーンを整えて、読み終わりの余韻を演出 |
| 情報補足や裏話を伝える | 紙面に載らなかったエピソードや裏話を紹介 |
9月ならではの魅力とテーマ設定のコツ
9月といえば、夏の余韻が残りつつも、秋の気配が本格的に感じられ始める時期ですよね。ちょうど季節の“はざま”にあるこの月は、自然の変化に敏感な読者の心に響きやすいタイミングでもあります。
編集後記ではこの季節感を活かし、「最近感じた涼しさ」や「秋の風物詩」「自宅でのちょっとした秋らしい体験」など、読者と共感しやすいテーマを選ぶのがおすすめです。
| テーマのアイデア | 9月らしい切り口の例 |
|---|---|
| 自然の変化 | 「虫の音が聞こえるようになりました」 |
| 食の楽しみ | 「新米やサンマを楽しみにしています」 |
| 行事・習慣 | 「秋分の日には家族でお墓参りを」 |
9月の編集後記は、「まだ暑いけれど秋も始まっている」という“中間地点”のニュアンスをうまく捉えると、グッと印象的な文章になりますよ。
9月の編集後記に使える季節のキーワード
この章では、9月の編集後記にぴったりな「時候の挨拶」や「季節の行事・風物詩」など、文章の季節感を演出するためのキーワードを紹介します。自然や文化のエッセンスを盛り込むことで、読者の共感を呼びましょう。
時候の挨拶と使い分けのポイント
9月は季節の移り変わりが感じられる月。気温や空気の変化に合わせた時候の挨拶を使い分けることで、文章の“季節感”がぐっと深まります。
例えば、9月上旬には残暑を意識した挨拶が適していますが、中旬以降は秋の深まりに合わせて言葉を変えていくのがポイントです。
| 時期 | おすすめの時候の挨拶 |
|---|---|
| 9月上旬 | 残暑の候/新秋の候/初秋の候 |
| 9月中旬 | 秋雨の候/秋涼の候 |
| 9月下旬 | 秋冷の候/仲秋の候/爽秋の候 |
「爽やかな風が吹き抜ける季節」や「コオロギの鳴き声が聞こえる夜」といった表現を織り交ぜると、自然に読者の季節感とリンクします。
行事・風物詩を効果的に取り入れる方法
9月には、秋分の日や敬老の日、中秋の名月といった季節を感じさせる行事が多数あります。編集後記にこれらのイベントを絡めることで、文章に“生活の温度”が加わります。
| 行事・イベント | 編集後記への活かし方 |
|---|---|
| 秋分の日・お彼岸 | 「家族でお墓参りに行き、季節の変化を感じました」 |
| 敬老の日 | 「祖父母に感謝の気持ちを伝える機会に恵まれました」 |
| 中秋の名月 | 「ベランダで月見団子を食べながら夜空を眺めました」 |
| 稲刈り・文化祭 | 「秋の収穫やイベントの賑わいを身近に感じています」 |
また、「秋の味覚」も外せないテーマですね。たとえばサンマや栗、新米などの話題は、多くの人の共感を得やすいです。「季節と暮らし」をつなげる意識を持つと、自然に読まれる文章になりますよ。
読者に響く書き出し例文集(9月編)
編集後記の書き出しは、読者の心をつかむ第一歩。特に9月は季節の変わり目ということもあり、自然の変化や日常の小さな出来事を交えた表現が効果的です。この章では、親しみやすさと上品さ、両方を備えた書き出し例を紹介します。
親しみやすいカジュアルな書き出し
カジュアルな文体の書き出しは、読者との距離をぐっと縮める効果があります。編集者の個人的な視点やちょっとした感想を織り交ぜるのがコツです。
| 文例 | ポイント |
|---|---|
| 残暑が続く日もありますが、朝夕は秋の気配が感じられる頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。 | 季節のグラデーションを感じさせる柔らかい語りかけ |
| 秋の虫の声が聞こえ始め、晩酌の時間が楽しみになる今日この頃です。 | 日常のささやかな変化を取り上げて共感を誘う |
| 朝晩はひんやりとした風が吹くようになり、ようやく寝苦しい夜から解放されました。 | 体感の変化を使ったリアルな季節感の演出 |
季節感を重視した上品な書き出し
フォーマルな場面や上品な印象を与えたいときは、時候の挨拶を活用した落ち着いた文調の書き出しが効果的です。特にビジネス文書や社外向けの媒体ではこのスタイルが好まれます。
| 文例 | 使いやすいシーン |
|---|---|
| 秋涼の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 | 社内報・学校報など、ややフォーマルな媒体 |
| 秋晴れの日が続く中、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 | 季節の話題を入口にした自然な導入 |
| 秋のお彼岸を迎え、日差しにも秋らしさを感じる今日この頃です。 | 行事を絡めた季節の挨拶 |
書き出しは文章の“顔”です。読み手が「読んでみよう」と思えるよう、自分の言葉で季節を描写することを意識してみましょう。
9月の編集後記 例文集(目的別)
ここでは、実際に使える9月の編集後記例文を目的別に紹介します。「親しみやすさを出したい」「季節感を表現したい」「フォーマルにまとめたい」など、使いたいシーンに応じて選べるように整理しています。
カジュアルで温かい印象を与える例文
読者に親近感を持ってもらいたい場合は、やわらかな口調と季節の話題を組み合わせた表現が効果的です。ちょっとした気遣いの言葉も添えると、読者との距離がぐっと縮まります。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| こんにちは。秋の訪れとともに、涼しい風が心地よく感じられるようになりました。虫たちの合唱がにぎやかで、ふとした瞬間に秋の深まりを実感します。皆さまも体調にはお気をつけくださいね。 | 自然の描写と読者への気遣いがポイント |
| 近所の稲刈り風景を眺めながら、今年も秋が来たんだなと感じています。季節の変わり目、みなさんもホッと一息つける時間が取れますように。 | 身近な光景と自分の感覚をセットで伝える |
季節の行事を取り入れた例文
中秋の名月や秋分の日、敬老の日など、9月の行事を織り交ぜると、読み手にとってタイムリーな内容になります。行事に自分の体験を交えるのがコツです。
| 例文 | 使える行事 |
|---|---|
| 先日、家族で月見団子を作りながら中秋の名月を楽しみました。空が高く、秋らしい夜にほっと一息つけました。 | 中秋の名月 |
| 秋分の日には久しぶりに実家へ。お彼岸ということもあり、家族とのつながりを改めて感じる一日となりました。 | 秋分の日・お彼岸 |
| 敬老の日に、祖母へ電話をかけて感謝の言葉を伝えました。少し照れくさかったですが、やって良かったと思います。 | 敬老の日 |
フォーマルで落ち着いた文体の例文
ビジネスや教育現場など、少しフォーマルな印象が求められる媒体では、時候の挨拶を冒頭に取り入れ、丁寧な語り口でまとめるとスマートです。
| 例文 | 特徴 |
|---|---|
| 秋涼の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。厳しい夏も過ぎ、ようやく過ごしやすい季節となりました。秋の行楽や読書の時間が皆様にとって実り多いものとなりますよう、心よりお祈りいたします。 | 時候の挨拶から入り、落ち着いた締め |
| 秋冷の候、朝夕の涼しさに秋の深まりを感じる頃となりました。日々の生活のなかで、季節の変化を楽しむ心のゆとりを大切にしていきたいと思います。 | 自然と内省を結びつけた構成 |
例文はあくまで「型」のひとつ。大切なのは、あなたの言葉で、あなたの感じた9月を描くことです。ぜひこの例文を参考に、自分らしい文章に仕上げてみてください。
読まれる編集後記を書くための5つのコツ
編集後記は短い文章ですが、ちょっとした工夫で「読まれる文章」に変わります。この章では、9月の編集後記をより魅力的に仕上げるための5つの実践的なコツを紹介します。
季節感をしっかり反映させる
「秋らしさ」や「9月ならではの空気感」を盛り込むことで、読者は文章を読んだ瞬間に“今”を感じ取ることができます。時候の挨拶や風物詩、食べ物などを自然に取り入れましょう。
| 季節感の演出例 | 使えるキーワード |
|---|---|
| 「空が高く澄み渡り、月が美しく感じられます」 | 中秋の名月、秋晴れ |
| 「スーパーに新米や栗が並び始め、秋の訪れを実感します」 | 新米、栗、秋の味覚 |
個人的な体験談を盛り込む
編集者自身のちょっとした体験や日常の出来事を加えることで、「人のぬくもり」が感じられる文章になります。小さな気づきや失敗談も、読み手には親しみをもって受け取られます。
| 体験の切り口 | 例文 |
|---|---|
| 日常の風景 | 「通勤途中に見かけたススキが秋の訪れを教えてくれました」 |
| 家族との時間 | 「敬老の日に祖母と話した時間が心に残っています」 |
読者への気遣いを忘れない
「お身体にお気をつけください」など、読者の生活や体調を思いやる一言を添えると、文章にあたたかさが加わります。特に季節の変わり目には効果的です。
体調や天候に触れる言葉は、読者の実感と重なりやすく、共感を呼びやすくなります。
文量とテンポを意識する
編集後記は300〜400文字程度が読みやすいとされます。長すぎると読者が疲れてしまい、短すぎると印象に残りません。1〜2文ごとに改行を入れ、テンポよく読み進められる構成を意識しましょう。
| 文の長さ | おすすめの構成 |
|---|---|
| 300〜400文字 | 導入→体験談→気づき→読者への言葉 |
| 短め(200文字程度) | 軽い季節の挨拶+一言感想 |
締めくくりの言葉で印象を残す
最後の一言は読者の心に余韻を残す大切なパーツ。次号の予告や感謝の言葉、今後の抱負など、シーンに応じて工夫しましょう。
たとえば、「秋の夜長にぴったりの本があれば、ぜひ教えてください」といった読者との交流を促す一言も効果的です。
まとめ — 9月の編集後記で秋の魅力を伝える
この記事では、9月の編集後記を書くうえで大切な考え方やテクニック、そしてすぐに使える例文までを幅広く紹介してきました。最後に、読者に伝わる文章に仕上げるためのポイントを整理しておきましょう。
| チェック項目 | 実践ポイント |
|---|---|
| 季節感が表現されているか | 時候の挨拶・秋の風物詩・行事を活用 |
| 個人的な視点があるか | 体験談や日常の気づきを交える |
| 読者とのつながりを意識しているか | 気遣いの一言や問いかけで親近感を高める |
| 文章の長さとテンポは適切か | 300〜400文字前後・改行を効果的に |
| 最後に印象的な締めがあるか | 感謝・抱負・次号予告などで印象づけ |
9月は季節の変わり目ということもあり、心や体にちょっとした変化が起こりやすい時期です。だからこそ、読者の気持ちに寄り添う一文が、思った以上に響くこともあります。
今回ご紹介した例文やコツをベースにしつつ、ぜひあなたらしい言葉で秋の空気を伝えてみてください。小さな編集後記が、誌面全体を温かく包む力になるはずです。