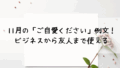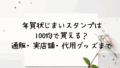「年賀状じまい」という言葉が当たり前になりつつある2025年。
郵便料金の値上げやデジタル化の普及を背景に、紙の年賀状からLINEやメールなどのデジタル挨拶へ切り替える人が増えています。
しかし「どう伝えれば失礼にならないのか」「どんな文例なら相手に誤解されないか」と迷う方も少なくありません。
本記事では、年賀状じまいを円満に伝えるためのマナーやタイミングを整理し、友人・職場・目上の方など相手別に使える文例を短文からフルバージョンまでご紹介します。
さらに、デジタル年賀状の便利な活用方法や、年賀状じまい後の関係づくりのコツも解説。
この記事を読めば「年賀状じまいをどう切り出すか」と悩む必要はなくなり、あなたらしい新しい挨拶スタイルを見つけられるはずです。
年賀状じまいとデジタル化のいま
ここでは、近年広がる「年賀状じまい」とデジタル化の現状を整理してみましょう。
紙からデジタルへ移り変わる背景を知ることで、なぜ多くの人が年賀状をやめるのか、その理由が見えてきます。
年賀状文化の衰退と郵便料金の影響
かつて日本では、年始に年賀状を送るのが習慣でした。
しかし、2004年には40億枚以上あった年賀状が、2025年には激減しています。
背景のひとつには郵便料金の値上げがあります。
特に2024年10月の値上げ(63円→85円)は、個人や企業の負担を大きくしました。
コスト増は「やめる理由」として非常に大きな要因になっています。
| 年 | 年賀状発行枚数 | 郵便料金 |
|---|---|---|
| 2004年 | 約40億枚 | 50円 |
| 2014年 | 約30億枚 | 52円 |
| 2020年 | 約20億枚 | 63円 |
| 2025年 | 約10億枚未満 | 85円 |
企業・個人に広がる年賀状じまいの動向
年賀状じまいは、個人だけでなく企業にも広がっています。
2025年の調査では、企業の約3社に1社しか年賀状を送っていないという結果が出ています。
さらに、約6社に1社は2024年を最後に年賀状じまいを決めました。
個人間でも、SNSやメールに移行した人が全体の6割以上を占めています。
「コスト削減」や「時間短縮」といった合理的な理由に加えて、環境意識や終活の観点からも広がっているのが特徴です。
つまり年賀状じまいは単なる流行ではなく、社会全体のライフスタイル変化の象徴と言えます。
なぜ「年賀状じまい」が増えているのか
年賀状じまいは一部の人の動きではなく、今や広く浸透しつつあります。
その背景には、デジタル化だけでなく社会の大きな変化が関わっています。
デジタル化とコミュニケーション手段の変化
LINEやメール、SNSの普及により、手軽に新年の挨拶ができるようになりました。
これまで「紙」でなければならなかったやりとりが、今ではスマホ一つで完結します。
特に若い世代では、年賀状を送った経験がほとんどない人も増えています。
スピード感や利便性を重視する生活スタイルに、デジタル挨拶は自然に溶け込んでいるのです。
| 世代 | 紙の年賀状派 | デジタル年賀状派 |
|---|---|---|
| 20代 | 約10% | 約80% |
| 40代 | 約35% | 約55% |
| 60代以上 | 約70% | 約25% |
高齢化・終活・環境意識の影響
もうひとつの理由は、高齢化や終活の広がりです。
「字を書くのがつらくなった」「整理を簡単にしたい」といった声が増えています。
また、ペーパーレス化の流れの中で、環境負荷を減らしたいという考えも強まっています。
突然やめるのではなく、きちんと感謝を伝えて区切りをつけることが、相手との良好な関係を保つコツです。
年賀状じまいは、単なる「やめる」ではなく「これからのつながり方を選び直す行為」と捉えると前向きに実践できます。
デジタル年賀状のメリットと注意点
紙からデジタルへ移行する人が増えているのは、単なる流行ではなく合理的な理由があるからです。
ここでは、デジタル年賀状ならではのメリットと、気をつけたい注意点を整理してみましょう。
コスト・時間削減の利点
まず大きな利点はコスト削減です。
はがき代や切手代、印刷代がかからず、無料で送れるサービスも豊富です。
さらに、スマホで数分あれば作成から送信まで完了します。
忙しい年末年始に時間を節約できるのは、現代のライフスタイルに非常に合っています。
写真・動画など表現の自由度
デジタル年賀状のもうひとつの魅力は自由度の高さです。
写真や動画、音楽をつけて送ることができるため、より個性的で思い出に残る挨拶が可能です。
たとえば、家族写真を添えたり、子どもの成長動画を送ったりするケースも増えています。
これは紙のはがきではなかなか実現できないポイントです。
| メリット | 具体例 |
|---|---|
| コスト削減 | 切手代・印刷代不要、無料アプリで送信可能 |
| 時短効果 | スマホで数分、忙しい年末でも対応可 |
| 表現の自由 | 写真・動画・音楽を添付できる |
| リアクションがわかる | 既読確認や即返信でコミュニケーションがスムーズ |
相手によっては失礼に見えるリスク
一方で、注意点もあります。
世代や関係性によっては「手抜き」と感じられてしまうことがあります。
特に年配の方や目上の方に対しては、紙の年賀状を好むケースがまだ多いのです。
相手に合わせて紙とデジタルを使い分けるのがマナーといえます。
また、グループ送信のまま同じ文面を送ると「心がこもっていない」と思われることもあります。
大切なのは手軽さではなく、相手に伝わる思いやりをどう表現するかです。
年賀状じまいを伝えるタイミングとマナー
年賀状じまいは「やめる」だけでなく、円満に関係を続けるための区切りです。
伝え方やタイミングを工夫すれば、相手に不快感を与えずに進められます。
最後の年賀状に添える一文の書き方
基本的には「最後の年賀状」に年賀状じまいを明記します。
「本年をもちまして年賀状でのご挨拶を最後とさせていただきます」といった一文を加えると自然です。
突然やめるより、あらかじめ告げる方が誠実と受け止められます。
感謝を伝えることの重要性
年賀状じまいは区切りであると同時に、これまでの感謝を伝える場でもあります。
「長年にわたりご厚情を賜り心より感謝申し上げます」など、これまでの関係を大切にする姿勢を示しましょう。
感謝の言葉を添えることで「終わり」ではなく「次のつながり」へとスムーズに移れるのです。
SNSやメールなど代替手段の案内方法
紙の年賀状をやめる代わりに、今後の連絡方法を案内すると親切です。
「今後はLINEやメールにて新年のご挨拶を続けさせていただきます」と伝えれば誤解を防げます。
また、世代や立場に応じて、暑中見舞いや季節のご挨拶に切り替えるのも有効です。
| 伝え方のパターン | 例文 |
|---|---|
| 感謝を添える | 「これまでいただいた温かいご厚情に心より感謝申し上げます」 |
| やめることを明記 | 「本年をもちまして年賀状でのご挨拶は最後とさせていただきます」 |
| 代替手段を案内 | 「今後はSNSやメールにてご挨拶を続けさせていただければ幸いです」 |
大切なのは「やめる理由」よりも「相手を思いやる気持ち」を示すことです。
相手別!年賀状じまいの文例集
年賀状じまいを伝える際は、相手との関係性に合わせた文面を選ぶのがポイントです。
ここでは、友人・職場・高齢者・家族ぐるみなど相手別に、短文とフルバージョンの例文をまとめました。
親しい友人・知人向け
カジュアルな関係では、やわらかい表現で十分です。
| タイプ | 文例 |
|---|---|
| 短文 | 「今年をもちまして年賀状でのご挨拶は区切りとし、今後はLINEでつながれれば嬉しいです。」 |
| フルバージョン | 「新年あけましておめでとうございます。 旧年中は楽しい時間をともに過ごせたこと、心より感謝しています。 誠に勝手ながら、本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶は最後とさせていただきます。 今後はLINEやSNSなど、より身近な方法でご連絡を続けられれば幸いです。 これからも変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。」 |
目上の方・職場関係者向け
敬意を保ちながら、丁寧な言葉を選びます。
| タイプ | 文例 |
|---|---|
| 短文 | 「誠に勝手ながら、本年をもちまして年賀状でのご挨拶を終了させていただきたく存じます。」 |
| フルバージョン | 「謹んで新春のお慶びを申し上げます。 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。 誠に恐縮ではございますが、本年をもちまして年始のご挨拶状の送付を控えさせていただきます。 長年にわたり頂戴したご厚情に深く御礼申し上げますとともに、 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。」 |
高齢・終活を理由にする場合
健康上の事情などを伝える場合は、正直かつ柔らかく。
| タイプ | 文例 |
|---|---|
| 短文 | 「高齢のため筆を取ることが難しくなりましたので、本年で年賀状を終わらせていただきます。」 |
| フルバージョン | 「新年おめでとうございます。 長きにわたり年賀状を通じてご挨拶を交わしていただき、心より感謝申し上げます。 私事で恐縮ですが、年齢を重ね執筆が難しくなってまいりましたため、 本年をもちまして年賀状でのご挨拶を終了させていただきます。 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。」 |
家族ぐるみのお付き合いの場合
家族全体での判断であることをやわらかく伝えましょう。
| タイプ | 文例 |
|---|---|
| 短文 | 「今年の年賀状を最後に、家族で相談の上ご挨拶の形を改めることにいたしました。」 |
| フルバージョン | 「新春のお喜びを申し上げます。 昨年中は家族ともども大変お世話になり、心より感謝しております。 誠に勝手ではございますが、家族で話し合いの上、本年をもちまして年賀状でのご挨拶を最後とさせていただきます。 今後はSNSやメールなど、別の形でご連絡させていただければと思います。 変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。」 |
デジタル化を理由にする場合
時代の変化を背景にスムーズに伝えられます。
| タイプ | 文例 |
|---|---|
| 短文 | 「今後はデジタルでのご挨拶へと切り替えさせていただきます。」 |
| フルバージョン | 「旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。 この度、時代の変化に伴い、今後はメールやSNSを活用した新年のご挨拶に切り替えさせていただきます。 紙の年賀状でいただいた温かいご厚情を忘れることなく、 今後も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」 |
文例はあくまで一例なので、自分らしい言葉にアレンジすることが大切です。
デジタル年賀状の活用アイデア
年賀状じまいをした後でも、デジタルを使えば挨拶の習慣を続けることができます。
ここでは、便利なサービスや工夫の仕方をまとめました。
LINE・メール・専用アプリの使い分け
最も一般的なのはLINEやメールでの新年挨拶です。
短文ならスタンプ付きメッセージ、丁寧に送りたいときは画像つきのカードを選ぶと良いでしょう。
また、専用アプリを使えばデザイン性の高い年賀状を数分で作成可能です。
相手や状況に応じてツールを使い分けると、より心のこもった挨拶になります。
無料テンプレートやデザインサイトの活用
インターネット上には無料で使える年賀状テンプレートが数多く公開されています。
近年は「年賀状じまい専用デザイン」も増えており、紙に代わって送るのに最適です。
シンプルから華やかなものまで幅広く揃っているため、相手に合わせたデザインを選べます。
| サービス | 特徴 |
|---|---|
| LINEスタンプ | 手軽でカジュアル。若い世代向け。 |
| メールテンプレート | ビジネスでも使いやすい定型文あり。 |
| 年賀状アプリ | 写真入りや動くカードが作れる。 |
| デザインサイト | 「年賀状じまい専用」デザインが無料公開。 |
心のこもったデジタル挨拶にする工夫
デジタル挨拶でも一手間加えることで印象は大きく変わります。
たとえば「昨年の思い出写真」を添えたり、相手ごとに一言アレンジを入れると喜ばれます。
返信が届いた場合は、なるべく早めに返すのも大切なマナーです。
一括送信だけに頼らず、相手を思う言葉を添えることが「ドライな印象」を防ぐ秘訣です。
デジタルだからこそ表現の幅が広がり、よりパーソナルな挨拶が可能になると言えます。
年賀状じまい後の関係づくり
年賀状じまいは「終わり」ではなく、むしろ新しい関係の始まりです。
ここからは、年賀状をやめた後にどのようにご縁をつないでいくかを考えてみましょう。
SNSや直接連絡でつながりを保つ方法
もっともシンプルなのは、LINEやSNSでのやり取りです。
年賀状を送らなくても「新年のご挨拶メッセージ」を投稿すれば、多くの人と一度に交流できます。
また、特に大切な相手には個別メッセージを送ると「ちゃんと覚えてくれている」と安心感を与えられます。
大事なのは「数」ではなく「心のこもった一言」です。
暑中見舞いや手紙で補う選択肢
「年賀状はやめたけれど、たまには紙で挨拶したい」という方には、暑中見舞いや残暑見舞いがおすすめです。
特に年配の方や紙文化を大切にしている方にとっては、年に一度でも手書きの手紙をもらえると特別な気持ちになります。
完全にやめるのではなく、シーンに合わせて形を変えることで関係性はより柔軟になります。
| つながり方 | 特徴 |
|---|---|
| SNS投稿 | 一度に多くの人へ挨拶できる。写真や動画も使える。 |
| 個別メッセージ | 相手に合わせた内容にできるため、気持ちが伝わりやすい。 |
| 暑中見舞い・残暑見舞い | 紙のやり取りを完全にやめず、年1回のご縁を保てる。 |
| 手紙 | フォーマルかつ温かみがあり、特別感が強い。 |
年賀状じまいは「縁を切る」ことではなく「新しい交流方法を選ぶ」ことだと考えると前向きになれます。
まとめ:感謝を伝えつつ新しい挨拶スタイルへ
年賀状じまいは「やめる」ことそのものが目的ではなく、これからもご縁を大切にするための選択です。
紙からデジタルへ移っても、人と人との心のつながりは形を変えて続いていきます。
本記事でご紹介したように、年賀状じまいを伝える際には感謝の言葉を忘れずに添えることが大切です。
さらに、相手や状況に合わせてSNSやメール、あるいは暑中見舞いなどの別の手段を選ぶことで、円滑な関係を保てます。
| ポイント | まとめ |
|---|---|
| 伝える姿勢 | 感謝を言葉にし、前向きなメッセージにする |
| 伝える方法 | 最後の年賀状に明記し、代替手段も案内する |
| その後の交流 | SNSや個別連絡、暑中見舞いなど柔軟に選ぶ |
「合理化」ではなく「これからもよろしく」という前向きな気持ちを伝えることが、相手にとっても安心につながります。
自分らしい方法で感謝を伝えることこそが、2025年以降のスマートな人間関係づくりの鍵になるでしょう。