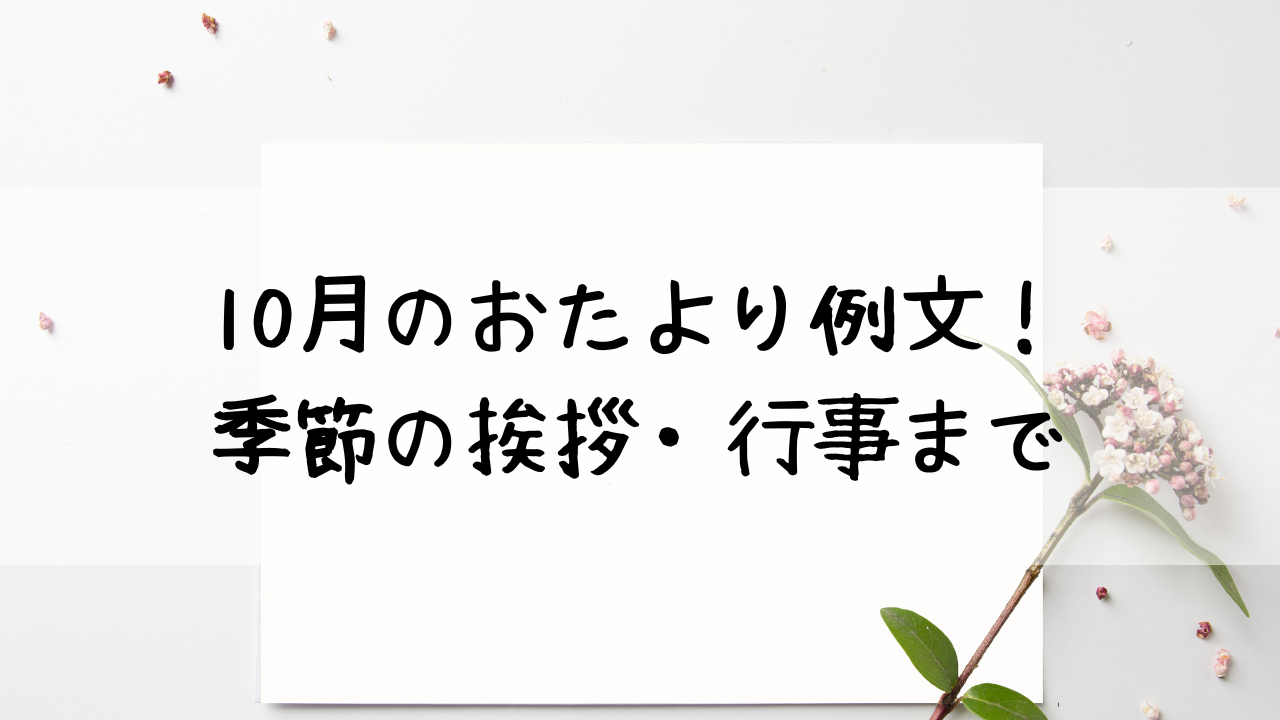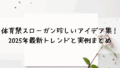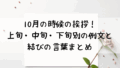10月は、紅葉や秋晴れが美しい季節であり、運動会や遠足、ハロウィンなど行事も盛りだくさんです。
子どもたちの成長や活動の様子を保護者に伝える「おたより」には、この時期ならではの季節感や行事の雰囲気を盛り込みたいですよね。
とはいえ「どんな書き出しにすればいい?」「行事のお知らせはどう書く?」と悩むこともあるはずです。
この記事では、10月のおたよりにそのまま使える例文を多数紹介し、季節の挨拶から行事案内、健康や生活の注意まで幅広くカバーしています。
園全体のおたよりやクラスだよりに応用できる表現はもちろん、0歳から5歳までの年齢別の例文も揃えました。
さらに、運動会・遠足・ハロウィンといった10月ならではの行事に使えるフレーズも収録。
この記事を読めば、忙しい時でも安心しておたよりを書けるアイデアが見つかります。
ぜひ参考にして、保護者にとっても読みやすく、子どもたちの姿が伝わる10月のおたよりを作ってみてください。
10月のおたよりの基本構成と書き方
10月のおたよりを書くときに迷いがちなポイントは、「どんな内容をどんな順番で入れればよいか」です。
ここでは、保護者にとって読みやすく、子どもたちの成長も自然に伝わるおたよりの構成と書き方の基本を紹介します。
おたよりに欠かせない5つの要素
おたよりには、毎月欠かせない基本の構成があります。
以下の5つを押さえておくと、読み手にとっても分かりやすい内容になります。
| 要素 | 内容例 |
|---|---|
| ① 季節のあいさつ | 「木々が色づき、秋の訪れを感じます。」 |
| ② 子どもの様子 | 「園庭を駆け回り、元気いっぱいに過ごしています。」 |
| ③ 行事予定 | 「運動会や遠足など、楽しいイベントがあります。」 |
| ④ 健康・保健 | 「朝夕の冷え込みに注意し、衣服の調整をお願いします。」 |
| ⑤ 保護者へのお願い | 「持ち物には必ず名前の記入をお願いします。」 |
この5つの要素をバランスよく盛り込むことで、自然に読みやすいおたよりになります。
季節感を自然に盛り込むコツ
10月といえば「紅葉」「秋晴れ」「虫の声」など、五感で楽しめる季節です。
こうした季節の言葉を一言入れるだけで、文章に温かみが出ます。
- 園庭の様子を描写:「どんぐりを見つけて嬉しそうに見せてくれました。」
- 気候に触れる:「朝晩は冷え込み、上着が必要な日が増えてきました。」
- 秋の楽しみを紹介:「焼き芋やハロウィンなど、子どもたちの笑顔が楽しみです。」
ただ季節を説明するだけでなく、「子どもたちがどう関わっているか」を添えると、保護者にとって具体的にイメージしやすいおたよりになります。
10月のおたよりで使える時候の挨拶と例文
10月のおたよりは、季節の雰囲気を伝える書き出しがとても大切です。
ここでは、すぐに使える時候の挨拶や、園だより・クラスだよりに応用できる例文を紹介します。
園だより全体で使える書き出し例文
園全体のおたよりでは、読み手に「秋らしさ」が自然に伝わる文章を意識すると良いです。
以下の例文は、そのまま使ったりアレンジしたりできます。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 「木々の葉が少しずつ色づき、秋の訪れを感じる季節になりました。」 | 紅葉を取り入れて、秋らしい情景を伝える。 |
| 「朝晩は肌寒く、温かい飲み物が恋しくなる頃です。」 | 気候の変化を具体的に伝える。 |
| 「園庭にはどんぐりや落ち葉が広がり、子どもたちは嬉しそうに拾い集めています。」 | 子どもの姿を盛り込み、身近に感じられる内容に。 |
園全体のおたよりは、保護者に「今月の雰囲気」を伝える窓口になる部分です。
クラスだよりに適した例文
クラスだよりは、子どもたちの様子がより身近に伝わる文章がおすすめです。
ここでは、年齢を問わず使いやすい例文を紹介します。
- 「すがすがしい秋晴れの下、子どもたちの笑い声が園庭いっぱいに響いています。」
- 「落ち葉を集めたり、虫の声を聞いたりと、自然と触れ合う楽しみが広がっています。」
- 「ハロウィンに向けて飾り作りをしたり、歌を歌ったりと、子どもたちのわくわくが高まっています。」
書き出し部分は、保護者が一番最初に読む部分なので「今月の子どもたちの姿が目に浮かぶ」文章を意識しましょう。
年齢・クラス別の10月おたより例文
子どもの成長段階に合わせて伝える内容を工夫すると、保護者にとって一層読みやすいおたよりになります。
ここでは、0歳から5歳までの年齢別に使える例文を紹介します。
0・1歳児向けの例文
0・1歳児さんは、身近な自然や音の変化を楽しむ姿を伝えるとよいでしょう。
| 例文 | ねらい |
|---|---|
| 「お散歩中に金木犀の香りが漂い、子どもたちは嬉しそうに空を見上げています。」 | 季節の変化を五感で楽しむ様子を共有。 |
| 「落ち葉を踏んでカサカサと音が鳴るたびに、にっこり笑顔を見せてくれます。」 | 音の楽しさを表現。 |
| 「大きな模造紙に手形スタンプを押して、秋らしい作品作りを楽しんでいます。」 | 制作活動を紹介。 |
2・3歳児向けの例文
好奇心いっぱいの年齢なので、「体験」や「発見」を取り入れた文章が伝わりやすいです。
- 「園庭でどんぐりを見つけ、『これなあに?』と友だちと話す姿が微笑ましいです。」
- 「さつまいもやかぼちゃを見て『おいしそう』と話し、給食の時間を楽しみにしています。」
- 「秋探しの散歩では、色づいた葉っぱを集めて袋いっぱいに持ち帰ってきました。」
「発見の喜び」や「友だちとのやりとり」を伝えると、保護者にとって成長が分かりやすいおたよりになります。
4・5歳児向けの例文
4・5歳児さんは、協力や挑戦の姿を伝えると家庭でも話題にしやすいです。
| 例文 | ねらい |
|---|---|
| 「運動会に向けてリレーやダンスの練習を重ね、仲間と励まし合う姿が見られます。」 | 努力や協力の大切さを共有。 |
| 「5歳児さんはハロウィンの飾りを自分たちで作り、相談しながら準備を進めています。」 | 自主性や創造性を伝える。 |
| 「友だちと役割を決めて劇遊びを楽しみ、表現力がどんどん育っています。」 | 集団活動の楽しさを紹介。 |
高年齢になるほど「挑戦」や「仲間との協力」を伝える文章を意識すると、保護者にとって成長を実感できる内容になります。
10月の行事に合わせたおたより例文
10月は運動会や遠足、ハロウィンなど子どもたちにとって楽しみな行事が盛りだくさんです。
ここでは、行事に合わせて使える具体的な例文を紹介します。
運動会のお知らせ例文
運動会は子どもたちの成長を大きく感じられる行事です。
練習の様子や意気込みを伝えると、保護者も本番を楽しみにしてくれます。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 「いよいよ運動会の季節です。リレーやダンスの練習を重ね、子どもたちは本番を心待ちにしています。」 | 期待感を高める。 |
| 「友だちと声をかけ合いながら、協力して練習に取り組む姿が見られます。」 | 協調性をアピール。 |
| 「当日は温かいご声援をよろしくお願いいたします。」 | 保護者への呼びかけを添える。 |
遠足の案内例文
遠足のお知らせでは、楽しさだけでなく準備物や安全面への配慮を盛り込むことが大切です。
- 「秋の自然を感じながら、みんなで公園へ遠足に出かけます。お弁当や水筒のご用意をお願いいたします。」
- 「どんぐりや落ち葉を見つけ、自然の中で友だちと過ごす時間を楽しみにしています。」
- 「歩く距離が少し長くなるので、履きなれた靴でのご参加をお願いします。」
遠足のお知らせには「準備物」と「楽しみの両面」を入れると、安心感と期待感を同時に伝えられます。
ハロウィン行事のお知らせ例文
ハロウィンは近年、多くの園で取り入れられるようになったイベントです。
簡単な仮装や制作活動を紹介すると、家庭との連携もしやすくなります。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 「10月31日にはハロウィンパーティーを予定しています。子どもたちと一緒に飾りを作り、準備を進めています。」 | 園での取り組みを伝える。 |
| 「当日は簡単な仮装をして参加します。ご家庭でも帽子やマントなど、ご準備をお願いいたします。」 | 保護者への協力依頼。 |
| 「『トリック・オア・トリート』の合言葉を元気に言いながら、楽しい交流をしたいと思います。」 | 子どもの楽しみを強調。 |
ハロウィンは日本ではまだ新しい行事なので、活動内容を具体的に書くと保護者も安心して参加できます。
10月のおたよりで伝える健康・生活のポイント
10月は朝晩の冷え込みや日中との寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期です。
ここでは、おたよりに盛り込みやすい健康や生活に関する伝え方を紹介します。
季節の変わり目の体調管理について
お子さまの健康を守るために、衣服の調整や生活リズムについて注意を呼びかける内容を入れておきましょう。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 「朝夕は冷え込む日が増えてきました。上着や着替えのご用意をお願いいたします。」 | 気温差への対応を依頼。 |
| 「体調がすぐれない時は、無理せずお休みいただきますようお願いします。」 | 無理をしない姿勢を伝える。 |
| 「手洗い・うがいを習慣にし、風邪予防を一緒に心がけましょう。」 | 家庭との協力を促す。 |
「お願い口調」ではなく「一緒に取り組みましょう」と伝えると、協力を得やすくなります。
衣替え・持ち物準備のお願い例文
10月は衣替えの季節でもあり、持ち物に関する案内を入れておくと安心です。
- 「衣替えに伴い、長袖・半袖を組み合わせて調整できるようご準備ください。」
- 「汗をかいたときに着替えられるよう、替えの下着や洋服を多めにご用意いただけると助かります。」
- 「持ち物には必ずお名前を書いていただきますようお願いいたします。」
持ち物については、トラブル防止のため「名前の記入」を繰り返し伝えるのが大切です。
まとめ|10月らしさを伝えるおたよりの仕上げ方
ここまで、10月のおたよりに使える構成や例文を紹介してきました。
最後に、仕上げのポイントを整理しておきましょう。
読みやすく伝わりやすい文章にする工夫
おたよりは長文になりがちなので、読みやすさを意識することが大切です。
| 工夫 | 具体例 |
|---|---|
| ① 短文を心がける | 「秋の風が心地よく、子どもたちは園庭を元気に走り回っています。」 |
| ② 箇条書きを使う | 「持ち物は①水筒 ②タオル ③お弁当です。」 |
| ③ 子どもの様子を添える | 「落ち葉を集めながら『きれいだね』と話す姿が見られます。」 |
「短く・具体的に・子どもの姿を添える」ことで、読む人の心に残りやすいおたよりになります。
保護者との信頼関係を深める一言の入れ方
おたよりの最後には、家庭とのつながりを意識した一言を加えると効果的です。
- 「ご家庭でも季節の自然に触れながら、秋を楽しんでいただければと思います。」
- 「日々の成長を保護者の皆さまと一緒に見守れることを嬉しく感じています。」
- 「今月もどうぞよろしくお願いいたします。」
最後のひと言は、保護者に安心感を与える大切な要素です。
子どもの姿を伝えながら、家庭とのつながりを感じられる言葉を添えることで、おたよりの価値がさらに高まります。