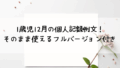12月に届く「お歳暮」は、一年の感謝を込めた大切な贈り物です。
その心遣いに応えるために欠かせないのが「お礼状」。
とはいえ、慌ただしい年末には「どんな文章を書けばいいのか」「例文をそのまま使いたい」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、お歳暮のお礼状について、12月にふさわしい時候の挨拶フレーズから、ビジネス・親戚・友人それぞれに使える例文までを網羅しています。
さらに、頭語から結語まで揃ったフルバージョン例文も掲載しているので、安心してそのまま使うことができます。
マナーを守りつつ、相手に温かさが伝わるお礼状を準備して、気持ちよく新年を迎えましょう。
12月に送る「お歳暮のお礼状」とは?
まずは、お歳暮のお礼状がどのような役割を果たすものなのかを整理していきましょう。
年末に届くお歳暮は、相手の心遣いや関係性を大切にする気持ちの表れです。
その思いやりに対して、感謝を形にして返すのがお礼状の役割です。
お歳暮のお礼状が大切にされる理由
お歳暮のお礼状は単なる形式的な挨拶文ではありません。
「いただいた贈り物を確かに受け取りました」という報告であると同時に、相手の思いやりを尊重する大切なメッセージです。
とくに年末は慌ただしく、連絡が遅れると「届いていないのでは?」と不安にさせてしまうこともあります。
お礼状をきちんと出すことで、安心感と誠意を伝えることができるのです。
| お礼状を出す目的 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 贈り物を確かに受け取ったことを知らせる | 相手の不安を解消できる |
| 相手への感謝を丁寧に伝える | 信頼関係を深められる |
| 季節感のある表現を添える | 年末らしい気配りを演出できる |
年末に特にお礼状が重視される理由
12月は「一年の締めくくり」という特別な意味を持つ時期です。
この時期にいただくお歳暮は、単なる贈り物以上に「今年もお世話になりました」という気持ちを込めて贈られます。
だからこそ、お礼状には形式だけでなく、心を込めた表現が求められるのです。
年末に交わされるお礼状は、翌年以降の関係を左右する大切な橋渡しだと言えるでしょう。
お歳暮のお礼状の基本マナー
ここでは、お歳暮のお礼状を書くときに押さえておきたい基本のマナーをまとめます。
形式的に見えても、このひと手間が相手への印象を大きく左右するものです。
「忙しいから後回しにしよう」と思わず、できるだけ早めに対応するのがポイントです。
送るタイミングと遅れたときの対応
お歳暮のお礼状は、贈り物を受け取って2〜3日以内に送るのが基本です。
すぐに投函できない場合は、メールや電話で「確かに受け取りました」と伝えた上で、後日正式なお礼状を出すと安心です。
もし一週間以上遅れてしまった場合は、「ご連絡が遅れましたことをお詫び申し上げます」と一文を添えると丁寧な印象になります。
| タイミング | 対応方法 |
|---|---|
| 2〜3日以内 | 手紙でお礼状を送る |
| すぐに送れない | メールや電話で受領を伝え、その後手紙を送る |
| 1週間以上経過 | 遅れたことをお詫びする一文を添える |
便箋・封筒・はがき・メールの使い分け
便箋や封筒を使った手紙は、もっとも丁寧で正式な方法です。
ビジネス関係や目上の方には、白無地の便箋と封筒が無難です。
親しい人へのお礼なら、季節感のある控えめなデザイン入りの便箋やはがきでも問題ありません。
メールやLINEは手軽ですが、フォーマルさには欠けるため、基本は親しい間柄に限定しましょう。
お礼状の基本構成(頭語〜結語までの流れ)
お歳暮のお礼状には、おおまかに次のような流れがあります。
これを押さえておけば、どんな相手にも失礼のない文章が書けます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 頭語 | 「拝啓」「謹啓」など |
| 時候の挨拶 | 「師走の候」「歳末の折」など12月らしい表現 |
| 相手の安否を気遣う言葉 | 「いかがお過ごしでしょうか」など |
| お礼 | 「このたびはご丁寧なお歳暮をいただき〜」 |
| 品物への感想 | 「社員一同で美味しくいただきました」など |
| 今後のお付き合いの言葉 | 「来年も変わらぬご厚誼を〜」 |
| 結語 | 「敬具」「謹白」など |
基本の流れを守るだけで、誰にでも通用するきちんとしたお礼状になります。
12月限定で使える時候の挨拶フレーズ集
お歳暮のお礼状には「時候の挨拶」を入れるのが基本です。
特に12月は、年末らしさや冬の雰囲気を表す言葉を選ぶことで、より丁寧な印象を与えられます。
ここでは、ビジネス向けと親しい人向けに分けて、すぐに使えるフレーズを紹介します。
ビジネスに適したフォーマル表現
目上の方や取引先に送る場合は、かしこまった時候の挨拶を使いましょう。
形式に沿った表現を選ぶことで、礼儀を重んじる姿勢が伝わります。
| 表現例 | 使い方 |
|---|---|
| 師走の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 | 一般的な12月の挨拶として無難 |
| 歳末の折、貴社におかれましてはますますご隆盛のことと拝察いたします。 | 会社宛に送る際におすすめ |
| 大雪の候、寒冷の折からお風邪など召されませんようお祈り申し上げます。 | 季節感を強調したいときに |
親しい人に使えるカジュアル表現
友人や親戚へのお礼状では、堅苦しすぎない言葉の方が自然です。
季節を感じさせつつ、柔らかく温かい雰囲気を出しましょう。
| 表現例 | 使い方 |
|---|---|
| 寒さも一段と増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 | 幅広い相手に使える |
| 年の瀬も押し迫り、慌ただしい毎日ですがお元気でいらっしゃいますか。 | 親戚や旧友への手紙にぴったり |
| 今年も残りわずかとなりましたが、体調を崩されていませんか。 | 親しい人への気遣いとして自然 |
避けたい表現とその理由
便利そうに見えても、かえって失礼に受け取られてしまう言葉もあります。
特にお礼状では、相手の気持ちを否定するような表現は避けましょう。
- 「お気遣いなく」 … 相手の心配りを否定する印象になる
- 「わざわざすみません」 … 感謝より負担を強調してしまう
- あまりに軽すぎる言葉 … 「ありがとう!」だけでは礼状として不十分
フォーマルさと親しみやすさを使い分けることが、12月のお礼状を成功させるコツです。
お歳暮お礼状の例文集【フルバージョンあり】
ここからは、すぐに使える具体的な例文を紹介します。
特に「フルバージョン例文」では、頭語から結語まで一通の手紙としてそのまま使える形にまとめました。
状況に合わせてコピペして調整すれば、すぐに送れるお礼状になります。
【フルバージョン】ビジネス向け例文(正式書簡)
拝啓 師走の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびはご丁寧に結構なお歳暮の品を賜り、誠にありがとうございました。
社員一同にてありがたく頂戴いたしました。
本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
来る年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げますとともに、貴社のさらなる発展を祈念いたします。
略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
| 場面 | ポイント |
|---|---|
| 取引先や顧客宛 | 「会社として」感謝を伝える文面 |
| 文末 | 「略儀ながら〜」で簡潔にまとめる |
【フルバージョン】親戚やかしこまった相手への例文
拝啓 歳末の折、皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
このたびは心のこもったお歳暮をお贈りいただき、誠にありがとうございました。
毎年こうしてお心遣いを賜り、深く感謝申し上げます。
いただいた品は、家族みんなで楽しませていただきました。
どうぞ良いお年をお迎えくださいますようお祈りいたします。
略儀ながら、まずは書中をもちましてお礼申し上げます。
敬具
友人・親しい人へのカジュアル例文
寒さが一段と厳しくなってきましたが、お元気ですか。
先日は素敵なお歳暮をありがとうございました。
家族みんなで美味しくいただき、ほっと温かい気持ちになりました。
年末のお忙しい時期かと思いますが、無理のないようお過ごしください。
来年も元気にお会いできることを楽しみにしています。
メールやLINEで送る場合の簡易例文
件名:お歳暮ありがとうございました
○○様
先日は素敵なお歳暮をお贈りいただき、ありがとうございました。
とても嬉しく、家族で早速いただきました。
年末で慌ただしい時期ですが、どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。
新しい年もどうぞよろしくお願いいたします。
ビジネスからプライベートまで、使える例文を揃えておくと安心です。
ケース別の応用例文
お歳暮のお礼状は、相手との関係や状況によって表現を少し調整する必要があります。
ここでは、よくあるケースごとの応用例文を紹介します。
「そのまま使える」形にしているので、必要に応じて調整してください。
妻が夫の代筆をする場合の例文
拝啓 師走の候、いよいよご多忙のことと存じます。
このたびは心のこもったお歳暮を賜り、誠にありがとうございました。
夫に代わりまして、厚く御礼申し上げます。
いただきました品は、家族そろって大切に使わせていただきます。
寒さも厳しくなってまいります折、どうぞ穏やかな年末をお過ごしください。
略儀ながら、書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
○○○(夫の名前)内
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 署名部分 | 夫の名前の横に「内」と添えるのが代筆ルール |
| 文面 | 「夫に代わりまして」と入れるとわかりやすい |
年賀状とお礼状を区別する例文
拝啓 歳末の候、いよいよご清祥のことと存じます。
このたびはご丁寧なお歳暮を頂戴し、心より御礼申し上げます。
年明けには改めて年賀のご挨拶を申し上げますが、まずはお歳暮へのお礼まで。
来る年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
遅れて出すときのフォロー例文
拝啓 寒冷の候、皆さまにおかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。
このたびはご丁寧なお歳暮を賜り、誠にありがとうございました。
ご連絡が遅くなりましたことを、まずは深くお詫び申し上げます。
いただきました品は、ありがたく使わせていただいております。
本年中のご厚情に心より感謝申し上げますとともに、来る年のご多幸をお祈りいたします。
敬具
状況ごとに一文を加えるだけで、誠実さがしっかり伝わります。
お礼状で気をつけたいNG表現と注意点
お歳暮のお礼状は、形式を守れば安心ですが、うっかり使ってしまうと相手に失礼になる表現もあります。
ここでは避けたい言い回しと、その理由をまとめました。
丁寧に書いたつもりが逆効果にならないよう、しっかり確認しておきましょう。
相手の気持ちを否定する表現
感謝を伝える場面で、相手の心遣いを否定してしまう言葉はNGです。
「そんなに気を遣わなくてもよかったのに」などは、一見優しいようでも相手の厚意を軽んじることになります。
| 避けたい表現 | 理由 |
|---|---|
| お気遣いなく | 相手の心配りを否定する印象になる |
| わざわざすみません | 「感謝」よりも「負担」を強調してしまう |
軽すぎる言葉や砕けすぎた表現
親しい相手なら多少カジュアルでも問題ありませんが、あまりにくだけすぎる言葉は避けましょう。
「ありがとう!」「めっちゃ嬉しい!」といった表現は、礼状としては不十分です。
長すぎて伝わりにくい文章
一文が極端に長くなると、読みにくさが先立ってしまいます。
お礼状は「端的で丁寧」が基本です。
感謝の気持ちをシンプルに伝えることを心がけましょう。
お礼状は「感謝を正しく伝える」ことが最優先。余計な表現を削ぎ落とすことが、かえって相手に誠実さを伝える近道です。
まとめ|12月のお歳暮には心のこもったお礼状を
12月に届くお歳暮は、一年の感謝を込めた特別な贈り物です。
だからこそ、お礼状を通じてこちらの感謝もきちんと伝えることが大切です。
この記事では、お歳暮のお礼状について以下のポイントを解説しました。
- お礼状はできるだけ早めに出すのがマナー
- 12月ならではの時候の挨拶を取り入れると丁寧
- フルバージョンの例文を参考にすれば安心
- 相手や状況に合わせて一文を調整する工夫が大切
- 「お気遣いなく」などのNG表現は避ける
特に12月は慌ただしい時期だからこそ、形式を整えつつ、あたたかみのある一文を加えるだけで印象が大きく変わります。
お礼状はマナーであると同時に、相手との信頼を深める絶好の機会です。
この記事で紹介した例文を活用して、気持ちがしっかり伝わるお礼状を準備してみてください。